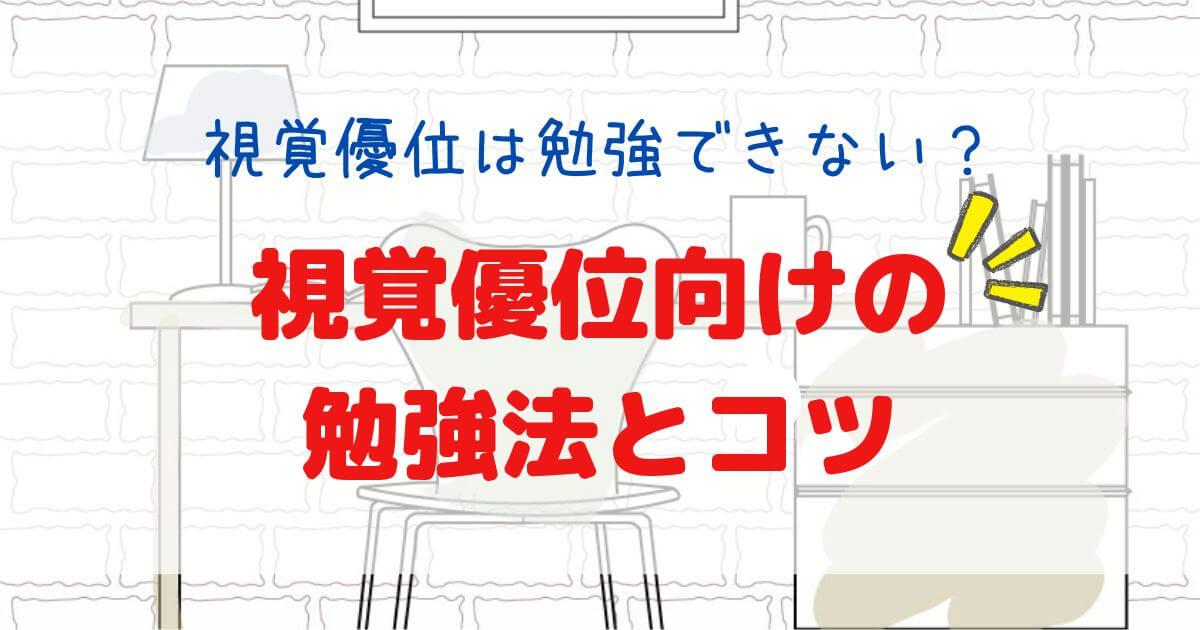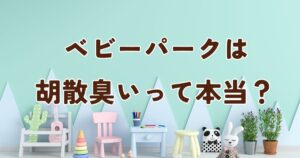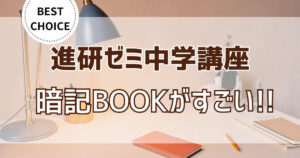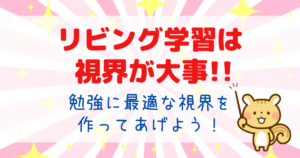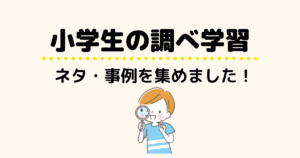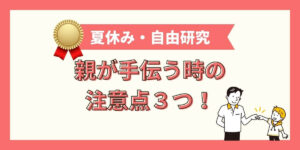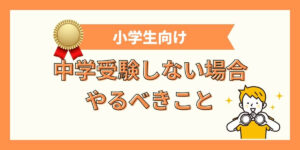視覚優位の子どもは「集中力が続かないから勉強が苦手」と言われることがありますが、本当でしょうか?
この記事では、視覚優位をいかした学習方法についてわかりやすく解説します!
この記事を書いている私自身が完全な視覚優位者です。地方公立高校から東京大学に進学し、現在は子ども2人の母です。自分自身の実体験をふまえ、視覚優位をいかした学習方法についてまとめました。
視覚優位はなぜ勉強ができない?
視覚優位の子供が必ずしも勉強ができないわけではありません。
しかし視覚優位の特徴と一般的な学習方法との間にギャップがあると、勉強が難しいと感じることがあります。
「教科書を読む」「先生の話を聞いてノートを取る」といった一般的な学習方法は、言語優位や聴覚優位の子供には適していますが、視覚優位の子供には理解しにくい場合があります。
視覚優位のお子さんでも、視覚優位の特徴をいかした学習方法で勉強することで効果も上がります。
視覚優位をいかした学習方法
視覚優位のお子さんは「見て覚える」のが得意です。
視覚的な教材を活用すると理解もしやすく学習効果も上がります。
学習ポスターを壁に貼る
「見て覚える」を最大限にいかせるのが学習ポスターです。
リビングの壁など目につきやすい場所に貼っておけば、無理なく自然に覚えることができます。
小学校の学習内容で暗記すべき内容をまとめた学習ポスターブックなどを利用すると便利です。
わが家では大きくて見やすい栄光ゼミナールの学習ポスターブックを購入しました。
「見て覚える」ための教材を使う
学習方法として昔は「書いて覚える」というのが一般的でしたが、今は「見て覚える」をコンセプトに作られた教材も増えています。
例えば、ドラえもんの国語おもしろ攻略 絵で見ておぼえる小学漢字1026は題名のとおり、「見て覚える」ことをコンセプトに作られています。
ドラえもんのマンガで楽しく漢字を学べるので、集中力が続きにくいお子さんにもおすすめです。
「マンガで覚える◯◯」というような学習漫画もおすすめです。
文字だけでなく絵をあわせて見ることで、視覚優位の子供でも理解しやすく記憶に残りやすいです。
短時間でできる教材を使う
視覚優位の子どもは集中力が続きにくいと言われています。
5分、10分といった短い時間でできる教材なら、途中で集中が途切れることもありません。
おすすめは学研プラスの「早ね早おき朝5分ドリル」のシリーズです。
「朝5分」となっていますがもちろん夜やってもかまいません。
短い時間で効果的な学習ができるように工夫されており、子供もあきずに続けることができます。
集中力を維持しやすい環境を作る
視覚優位の子供が勉強できない理由としてよく挙げられるのが、「まわりに気を取られて集中できない」という点です。
では学習に集中するためにはどうしたらよいのでしょう?
いちばんいいのは視界に入る邪魔なものを片付けてしまうことです。
すぐに片付けるのが難しい場合は、視界をさえぎるグッズを利用するのがおすすめです。
塾の自習室などもそうですが、視界をさえぎることで目からよけいな情報が入らず勉強に集中することができます。
\おすすめ!視界をさえぎるパーテーション/
教材は「見やすさ」で選ぶ
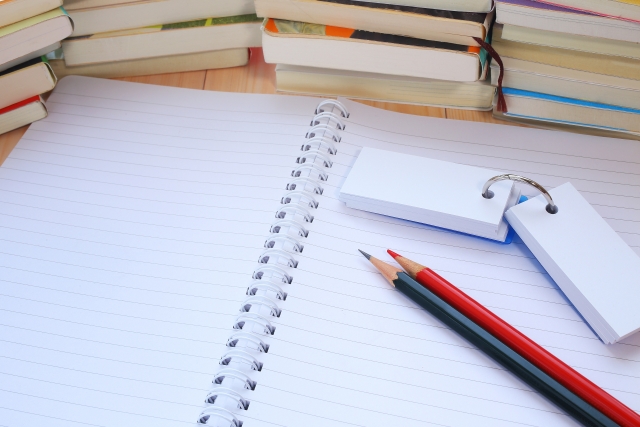
例えば小学生向けの国語辞典はカラー印刷と白黒印刷の2種類があります。
「見て覚える」ならわかりやすいカラー印刷がよさそうですが、そうでもありません。
お子さんによっては色に気をとられて、書いてあることが頭に入りにくい場合もあります。
例えば私の場合は、↓以下の要素が気になります。
●本(ページ)の大きさ
→一度に覚えやすい大きさがある。
●色使い
→自分が見やすい色使いがよい。内容によっては白黒のほうがいい場合もある。
●図や文章の配置
→自分が見やすい配置がよい。
●フォント(字体)
→自分の好きなフォントがよい。好みでないフォントだと覚えにくい。
細かく書きましたが、これらの要素をいちいち気にする必要はありません。
お子さんがパッと見て直感的に「見やすい!」と感じたものを選びましょう。
口コミやレビューで評判のよい人気の参考書でも、お子さんが「見にくい」と感じるものはおすすめしません。買ってもおそらく読まないでしょう。
視覚優位の子供にとって、「見やすさ」はとても大事です。
大事なところにマーカーを引く必要はない
一般的な学習方法では、教科書や参考書などの大事なところに蛍光ペンや赤ペンなどで線を引いて目立つようにしますよね。
しかし、視覚優位のお子さんはこの「線を引く」のがあまり好きではない場合があります。私自身がそうでした。
線を引くのがいやな理由は、線を引いた箇所が目立ちすぎてそこばかり目に入ってしまうからです。
逆に線を引かないことによって、ページ全体を理解しやすいと感じました。
ただし、学校では授業中に先生から「ここに線を引いて」と言われることがありますよね。
私はあまり目立たないように黄色の色鉛筆で線を引いていました。
黄色の色鉛筆だと線が多少曲がっても目立たず気にならないので、定規を使わずにフリーハンドでさっと引けるのもよかったです。
もちろんマーカーを引いたほうが覚えやすいというお子さんもいるでしょう。
大事なのは一般的な学習方法を無理にやらせないことです。
特に「見た目」や「見やすさ」にかかわる点は、「好きな色の筆記用具を選ばせてあげる」など、お子さんの好みを優先するとよいと思います。