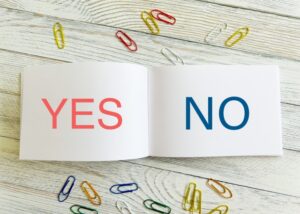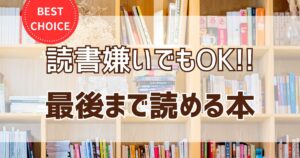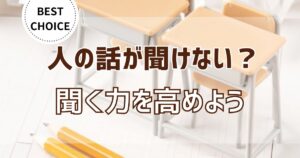「ここまでがんばってきたのに、辞めてしまうのはもったいない」
子どもが習い事を辞めたいと言ってきたとき、そう考える親御さんは少なくないでしょう。
ピアノ、英語、サッカーなど…せっかく始めた習い事を辞めるのは、親にとっても子どもにとっても大きな決断です。
この記事では、子どもの習い事の辞め時を見極めるポイントや、「もったいない」の気持ちを整理する方法を、親目線でくわしくお伝えします。
\学年別・家庭学習でやるべきこと/
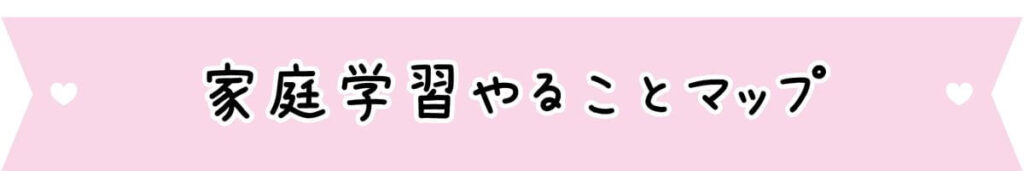
習い事を辞めるのが「もったいない」と感じるのはなぜ?
「習い事を辞めたい」と子どもが言い出したとき、親が「もったいない」と感じる理由は大きく分けて3つあると考えます。
【習い事を辞めるのがもったいないと感じる理由】
1. 時間と努力の積み重ね
2. 子どもの将来への期待
3. 経済的な投資への未練
時間と努力の積み重ね
子どもが習い事を続けてきた努力や時間、親が送迎やサポートに費やした労力を思うと、今辞めるのはもったいないと感じてしまいます。
「もう少し続ければ上達するかもしれない」「今やめたらこれまでのがんばりが無駄になる」と感じるのは、親として子どもの成長を願うからこそです。
また、「もったいない」とは少し違いますが、習い事を辞めると困難からすぐに逃げてしまう「辞め癖(やめぐせ)」がつくのではないかと心配になることもあります。
子どもの将来への期待
習い事は子どものスキルや可能性を広げてくれます。
「英語は将来役に立つ」「スポーツで体力や協調性が育つ」と期待していた親にとって、辞めることはその可能性を閉ざすように感じられるかもしれません。
この「もったいない」という気持ちは、親として子どもの未来を真剣に考えるからこそ湧いてくるものです。
でもこの感情に振り回されると、子どもの本当の気持ちや最適な選択を見逃してしまうこともあります。
経済的な投資への未練
習い事にはレッスン料、教材費、場合によっては楽器やユニフォームの購入など、大きな費用がかかります。
例えば、ピアノ教室ならピアノ本体や発表会の費用、英語教室なら高額な年間契約など。親としては「ここまでお金をかけたのに…」と思うのは当然です。
この経済的損失感が「もったいない」の要因の1つになることもあります。
「もったいない」という親の気持ちと向き合う

子どもが「辞めたい」と言い出したとき、親がまず抱く感情が「もったいない」かもしれません。
私も2人の子どもの子育てを通して、何度もこの思いを経験しました。
辞めることは本当に「もったいない」のでしょうか?
この「もったいない」という思いは、子どもの成長を願う親心から生まれています。
その「もったいない」という思いが、本当に子どもの幸せや成長にとって邪魔になっていないか、親は考えなければいけませんね。
習い事の辞め時を見極める5つのチェックポイント
子どもの習い事を辞めるべきか続けるべきか迷ったときの、5つのチェックポイントを紹介します。
【習い事の辞め時を見極める5つのチェックポイント】
1. 心身の不調
2. モチベーションと目的の明確な喪失
3. 人間関係の問題
4. 子どもの成長段階
5. 経済的・時間的負担
心身の不調
言葉よりも正直なのが、子どもの心と身体の反応です。
習い事の日やその前に、以下のような状態が継続して見られる場合は、心身に大きな負担がかかっているサインかもしれません。
- 体調の変化:習い事の直前にお腹が痛くなる、頭痛を訴える、微熱が出る、食欲が落ちる。
- 感情の変化:笑顔が減る、イライラが増える、以前より泣きやすくなる、無気力になる。
- 睡眠の変化:寝つきが悪くなる、夜中に何度も目を覚ます。
これらは、子どもが言葉にできないストレスや苦痛を、身体が代弁している状態です。「疲れているだけ」と見過ごさず、「習い事の前だけ」という継続的なパターンがあるかを確認し、子どもの「身体の声」に真剣に耳を傾けましょう。
子どもの健康と幸福が最優先です!
モチベーションと目的の明確な喪失
「技術的な壁にぶつかって一時的にやる気をなくしている」のではなく、その習い事に対する根本的な興味や目標が失われてしまった場合です。
- 練習への姿勢:習い事そのものに楽しさがなく、義務感だけで通っている。
- 目的の達成と次の目標の欠如:当初の目標(例:泳げるようになる、初段を取る)を達成し、本人が「もう十分」と満足している。
- 新しい興味の出現:他に「どうしてもやりたいこと」が明確に見つかった。
スランプで「辞めたい」という時は、「もう少し頑張れば乗り越えられるよ」と励まし、小さな目標を設定してサポートする価値はあります。
しかし、本人が「好き」という気持ちを完全に失い惰性で続けている状態は、その時間とエネルギーを別の本当に熱中できることに使うチャンスを奪っているかもしれません。
子どもの興味や意欲子どもが習い事に対して全く興味を示さなくなった、または「辞めたい」と繰り返し言う場合は、無理に続けるよりも別の興味を探す方がよい場合もあります。
逆に、少しでも楽しさや目標があるなら続ける価値があるかもしれません。
人間関係の問題
習い事の内容ではなく、指導者や友達との人間関係が原因で行きたがらないケースも多くあります。
- 指導者との相性:先生の指導方法が厳しすぎる、萎縮してしまう、理不尽に感じる。
- 友達との関係:仲間外れにされている、いじめがある、チーム内の雰囲気が悪い。
人間関係のトラブルは、親が介入しても解決が難しい場合や、教室自体の方針が変わらない限り改善しないこともあります。
習い事は本来、学校とは別の居場所や成長の機会を提供する場です。そこが「耐える場所」になってしまったら、そのメリットは失われます。
先生に相談したり、クラスや曜日を変えるなどの工夫をしても改善しない場合は、環境を変えることを検討しましょう。
子どもの成長段階
小学生はまだ自分の気持ちや将来の価値を完全に理解できません。
「辞めたい」が一時的な感情か、深く考えた結果かを、親が冷静に見極める必要があります。
経済的・時間的負担
親や家庭全体にとって、習い事が大きな負担になっている場合も見直しのサインです。親のストレスが子どもに影響することもあります。
無理のない範囲で習い事が続けられるか検討しましょう。
子どもの「辞めたい」の本音を見極める
子どもが「辞めたい」と言う背景には、さまざまな理由が隠れている可能性があります。
「習い事をやめたい」という子どもの言葉が、単なる一時的な甘えなのか、それとも深刻なSOSなのか。親はそれを見極める必要があります。
子どもが「辞めたい」と言う主な理由と親の対応をまとめたので、参考にしてみてください。
理由1:習い事が楽しくない
- 背景:レッスンがつまらない、先生や仲間との相性が合わない、内容が難しいなど、楽しさが感じられない場合。
- 対応:子どもに「どんなときに楽しくない?」と具体的に聞いてみましょう。例えば、「先生が怖い」「練習が大変」と言うなら、教室の変更やレッスン内容の見直しを提案できるかもしれません。
理由2:疲れや時間の負担
- 背景:学校や他の習い事との両立が難しく、疲れが溜まっている場合。特に小学生は体力や時間管理のスキルが未熟です。
- 対応:スケジュールを見直し、習い事の頻度を減らす(週2回を1回に変更など)や、休会制度を利用するのも一つの手です。
理由3:モチベーションの低下
- 背景:最初は楽しかったけれど、上達が感じられない、目標が見えない、友達が辞めたなどの理由でやる気が下がっている場合。
- 対応:子どもの目標を再設定する(例:発表会で1曲弾く、試合に出るなど)か、一時的に休んでリフレッシュする時間を与えるのも効果的です。
辞める前に親が子どもに対してできること
習い事を辞める決断をする前に、親が子どもに対してできること・やってみてほしいことをまとめました。
子どもの気持ちを受け止める
子どもが「習い事を辞めたい」と親に言うのは勇気がいります。頭ごなしに「もったいないから続けなさい」と言うのはやめましょう。
「なぜ?」と理由を追求する前に、「そうか、大変だったね」「つらいんだね」と、子どもの気持ちをそのまま受け止めてあげてください。
親に話を聞いてもらえただけで、気持ちが整理され「もう少しがんばってみようかな」と自発的に言えるようになることもあります。
「一時休会」という選択肢
完全に辞めてしまう前に、数週間から数ヶ月の「休会」を提案してみるのも有効です。
距離を置くことで、子どもが「やっぱりやりたい」「休んでいる間に、別の場所で頑張りたい」など、自分の本心に気づくことがあります。
小さな目標を設定する
「次の発表会まで」「次の級や段の試験まで」など、期限付きの小さな目標を親子で一緒に設定し、「これが終わったら、改めて続けるか辞めるかを決めよう」と約束します。
最後までやり遂げたという達成感や、けじめをつける経験は、「やり抜く力」の芽を摘まずに、次のステップへ移行する手助けになります。
辞めることは「次の成長」への投資と考えよう
習い事を辞めることは、決して「失敗」や「後退」ではありません。
むしろ、合わないものに費やしていた時間とエネルギーを解放し、子どもが本当に夢中になれる「何か」を探すための「次の成長への投資」と捉えることができます。
- 自己選択の経験:親に強制されたのではなく、自分で考え、決断し、先生に感謝を伝えて辞めるプロセスは、自立心と社会性を育みます。
- 時間の余裕:空いた時間に友達と遊んだり、本を読んだり、家族とゆっくり過ごしたりすることで、精神的なゆとりと新たな興味が生まれます。
- 新しい挑戦の機会:辞めたことでできた空白に、新しい習い事や、学校の勉強、趣味など、本当に好きなことが見つかる可能性が生まれます。
親の「もったいない」という気持ちよりも、子どもの「辞めたい」というサインに隠された理由と、次の成長への可能性を信じることが、親の最も大切な役割です。
習い事の終わりは、子どもの成長の終わりではありません。それは、彼らが自身の意思で選ぶ、新しい物語の始まりなのです。親として、子どもが納得して前向きに次のステップへ進めるよう、最後まで温かくサポートしてあげましょう。
「もったいない」を乗り越える4つの方法
親自身の「もったいない」という気持ちを整理し、前向きな決断をするための方法を紹介します。
費用の損失感を整理する
- 返金や休会制度を確認:多くの教室では途中解約や休会の制度があります。契約内容を確認し、経済的損失を最小限に抑える方法を探りましょう。
- 投資の価値を再評価:これまでにかけた費用は、子どもの経験や学びにつながっています。「無駄」ではなく「成長の過程」と捉えると気持ちが軽くなります。
スキルの活かし方を考える
辞めた後でも、習ったスキルは別の形で活かせます。例えば、ピアノを辞めても音楽の基礎知識は残り、別の楽器や趣味に活かせるかもしれません。英語なら、オンラインツールや日常会話で続けることも可能です。
子どもの主体性を尊重
子どもの「辞めたい」という意思を尊重することで、自己決定力や自己肯定感が育ちます。親が「もったいない」と押し付けるよりも、子どもが自分で選んだ道を応援する方が、長期的な成長につながります。
新しい可能性を探る
習い事を辞めることは、新たな挑戦のチャンスでもあります。子どもが興味を持つ別の活動(スポーツ、芸術、プログラミングなど)を一緒に探すことで、「もったいない」から「次への一歩」へと気持ちを切り替えられます。
他の親の体験談
実際に習い事を辞めた方の体験談を見るのもいいです。
Aさん(小学3年生の親):娘が水泳を辞めたいと言い出し、最初は「高い水着を買ったのに」と抵抗感がありました。でも、辞めた後に絵画教室に通い始め、娘の笑顔が増えました。「辞めるのは終わりではなく、新しいスタートだった」と感じています。
Bさん(小学5年生の親):息子のサッカーが負担になり、休会を選択。1カ月の休みでリフレッシュでき、再びやる気が出て戻りました。「一度離れるのも大事」と気づいたそうです。
習い事を辞めるかどうか決断するための具体的なステップ
親子で穏やかに話し合い、辞めたい理由を具体的に把握する。
休会・回数の変更・別の教室への移行など、辞める以外の選択肢を検討する。
先生やコーチに子どもの状況を伝え、アドバイスをもらう。
例えば「あと1カ月続けてみて、それでも辞めたいなら決めよう」など期間を決める。
辞める場合は子どもが達成感を持てるように、発表会や試合で締めくくるのも良い方法です。
まとめ:習い事を辞めることは「もったいない」ではない
子どもの習い事を辞める決断は、親にとって簡単ではありません。
「もったいない」という気持ちに縛られず、子どもの気持ちや家庭全体のバランスを考えることが大切です。
辞めることは終わりではなく、新しい可能性への一歩。子どもの笑顔と成長を第一に、親子で納得できる選択をしてください。
もしお子さんの習い事の辞め時で悩んでいるなら、まずはお子さんとじっくり話してみてくださいね。親子の絆を深め、最適な決断に導いてくれるはずです。