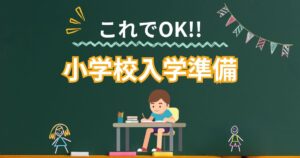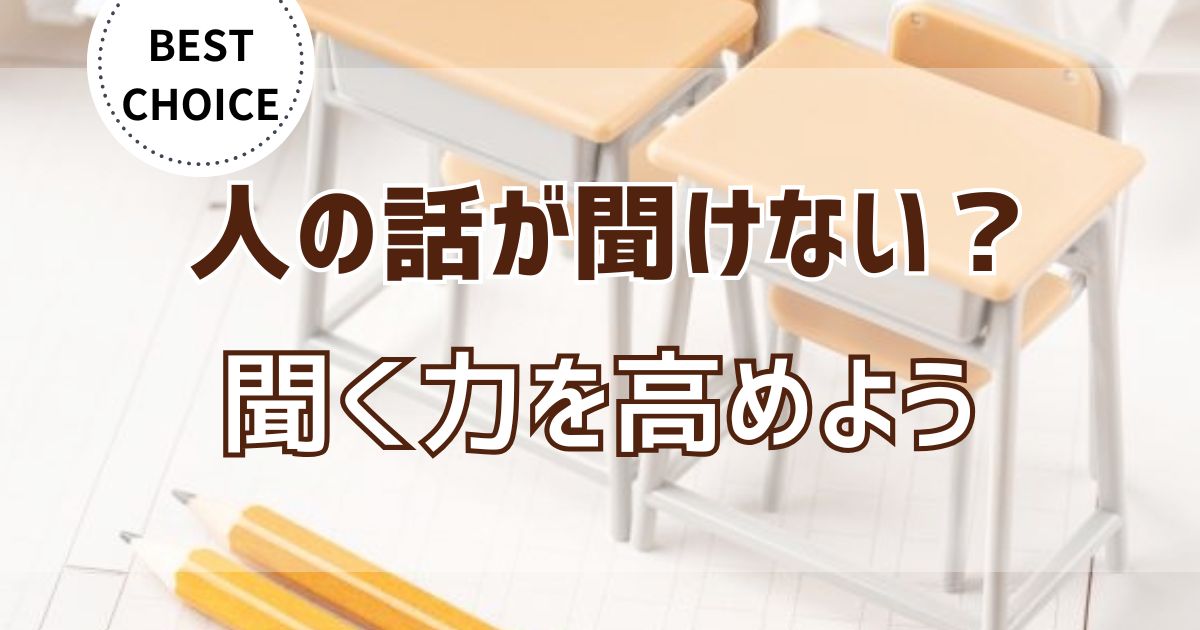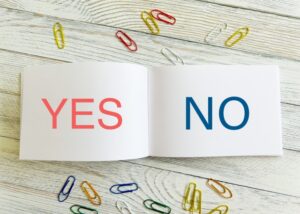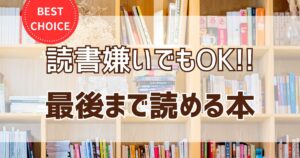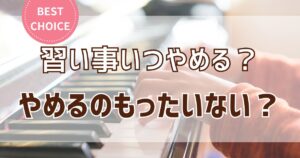「うちの子、全然話を聞いてくれない」
「何度言ったらわかるの!」
お子さんを持つ親御さんなら、一度はこんな悩みを抱えたことがあるのではないでしょうか。
何度注意しても上の空、指示を伝えてもすぐに忘れてしまう…。
この記事では、
▶子どもが人の話を聞けない原因
▶聞く力の高め方
について、わかりやすく解説します!
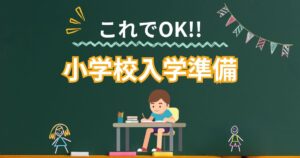
【人の話を聞けない子ども】原因と聞く力の高め方
お子さんが人の話を聞けないのは、親御さんの育て方のせいではありません。
子どもの発達段階や脳の機能的な特性など、そして何より「聞く力」がまだ育ちきっていないという原因があると考えられています。
【子どもが人の話が聞けない主な原因】
1. 発達段階によるもの(集中力・興味関心の移行)
2. 言葉の理解や処理能力によるもの
3. 脳の機能的な特性(ADHD・ASDの特性)
原因1:発達段階によるもの(集中力・興味関心の移行)
特に幼児期の子どもは、目の前の「興味があること」に夢中になる特性があります。
大人が話しかけた時にお子さんが積み木やお絵描きに集中していたら、そちらへの関心が勝ってしまい、大人の声が耳に入ってこないのは自然なことです。
また、集中力が続く時間も大人よりずっと短いです。
長い話や抽象的な指示は最後まで聞いていること自体が難しいのです。これは成長とともに改善していく部分ですが、「聞く」ための土台作りは必要です。
原因2:言葉の理解や処理能力によるもの
話を聞くためには、聞こえた音を意味のある言葉として認識し、内容を理解する必要があります。
このプロセスがスムーズにいかない場合、話を聞き逃したり理解できなかったりします。
- 語彙力・理解力不足:使われた言葉の意味がわからないと、話全体が理解できません。
- 聴覚情報の処理が苦手(聴覚情報処理障害):音としては聞こえていても、それを言葉として脳内でスムーズに処理するのが苦手な特性を持つ子どももいます。雑音が多い場所では特に聞き取りづらくなります。
原因3:脳の機能的な特性(ADHD・ASDの特性)
発達障害の特性が「話を聞けない」という形で現れることもあります。この場合は専門の医師にご相談ください。
- ADHD(注意欠陥・多動性障害)の特性:「不注意」の特性がある場合、話への注意を維持したり、細かな指示を記憶したりすることが困難になります。「衝動性」の特性がある場合、相手の話が終わる前に思わず口を挟んでしまうことがあります。
- ASD(自閉スペクトラム症)の特性:言葉の裏にある意図や比喩表現、場の空気を読み取ることが難しいため、会話の「暗黙のルール」に沿った受け答えが難しく、「話を聞かない」ように見えてしまうことがあります。
「聞く力」をトレーニングする教材
「聴覚情報処理能力」や「ワーキングメモリ」といった基礎的な聞く力は、専門的な教材で意識的にトレーニングすることで集中的に伸ばすことができるとされています。
聞く力のトレーニングに特化した教材を取り入れて、お子さんの聞く力を楽しく伸ばしていきましょう!
手に入りやすい市販の教材で、幼児〜小低学年向けの2つを紹介します。どちらも専門家監修で、聞く力を高めることに特化したドリルです。
「きくきくドリル」シリーズ
【「きくきくドリル」シリーズの特長】
・「人の話をしっかり聞く力」を養う
・集中力や記憶力、話す力の土台を育てる
・QRコードで手軽に音声が聞ける
\初めての聞く練習に!4〜5才向け/
「きくきくドリル」は、数多くの著書で有名な精神科医である和田秀樹先生監修のドリルです。
QRコード(またはアプリ)で音声を聞いて問題に答えるので、親が読み上げる必要がなく手軽に取り組めます。
「STEP1(はじめて編)」は簡単な音の区別から始まり、「STEP2(入学準備編)」「STEP3(発展編)」では徐々に複雑な指示を記憶する課題へステップアップします。
遊び感覚で親子で楽しみながら聞く力を無理なく伸ばせると、人気のドリルです。
\小学校入学準備に!5〜6才向け/
\集中して授業を聞く練習に!6〜7才向け/
「ワーキングメモリーとコミュニケーションの基礎を育てる 聞きとりワークシート」シリーズ
【「聞きとりワークシート」シリーズの特長】
・実際の療育で使用した実践的な教材
・LD、ADHD、自閉症スペクトラム障害を持つお子さんやその傾向のあるお子さん向け
・イラストが多く字が読めない子どもでも楽しく取り組める
\言われたことを聞く!5才〜向け/
NPOフトゥーロ監修の「ワーキングメモリ(作業記憶)」の強化に焦点を当てたワークシートです。
「聞きとりワークシート」シリーズは3冊あります。
①言われたことをよく聞こう編/対象年齢5才〜
②大事なところを聞きとろう編/対象年齢6才〜
③イメージして聞こう編/対象年齢7才〜
※対象年齢は目安なので、実際の年齢にとらわれずお子さんにあったものを選んでください。
他人とコミュニケーションを取る上で基本となる「聞いて、覚えて、応じる」ことを、クイズやゲーム形式で楽しみながら練習できます。
実際の療育の中で子どもたちに向けて作成し使用した実践的な教材なので、「使いやすい」「効果が感じられる」という口コミが多いです。
楽しみながら使えるように工夫されているので、親子で聞く力を高める練習をするのにぴったりです。
\大序なところを聞き取る!6才〜向け/
\イメージして聞く!7才〜向け/
男の子は「聞く力」を育てる、女の子は「見る力」を育てる
わが家の長男が小さかった頃、私が話しかけても全然話を聞いていないと感じることがよくありました。
特に母親と男の子のお子さんだと性別が違うために、よけいに理解できずにそう感じるようです。
\男の子を育てる親の困ったを解決!/
「男の子は脳の聞く力を育てなさい」は、発達脳科学の専門家である加藤俊徳先生が、1万人以上の脳をMRIで分析した知見を基に執筆された本です。
男の子は生まれつき「聞く脳」の発達が遅れやすく、話を聞かない・落ち着きがないなどの行動は「聞けない脳」が原因だと指摘します。
具体的なアドバイスをたくさん提案してくれているので、すぐに実践することができます。
います。男の子の「困った」行動の9割を解決するヒントがたくさん得られます。
口コミなどでも「息子の集中力が劇的に変わった!」という声が多く、男の子を持つ親必読の一冊です。
女の子の親御さん向けには同じ加藤先生執筆の「女の子は脳の見る力を育てなさい」がおすすめです。
女の子は男の子より成長が早いので、しっかりしていて子育ても楽そうに思えますが、実はそんなことはありません。
口が達者で言い訳ばかりするかと思えば、逆に苦手なことは極端に消極的だったり。
「女の子は脳の見る力を育てなさい」は、女の子の子育ての困ったを解決するのにおすすめの1冊です。
\女の子の親向け・実は難しい女の子の子育てに/
まとめ:人の話を聞く力を育てよう
「人の話を聞く力」は、お家の中だけでなく学校の授業をはじめとした全ての集団生活において基礎となる大切な能力です。
「聞く力」が伸びれば、お子さん自身にとっても親御さんにとっても生活にプラスになることはまちがいありません。
この記事で紹介した専門の教材などを利用した適切なトレーニングで、「聞く力」をしっかりと確実に伸ばしてくださいね!